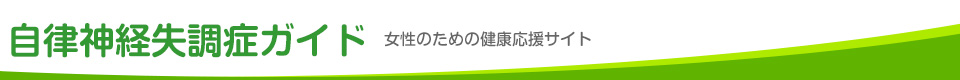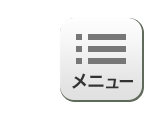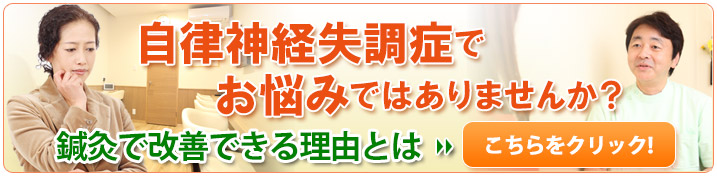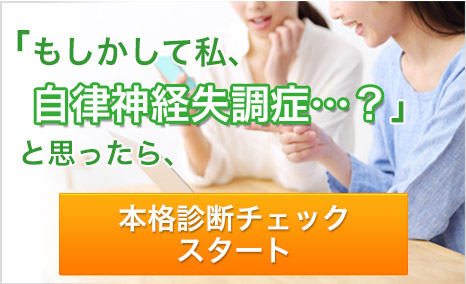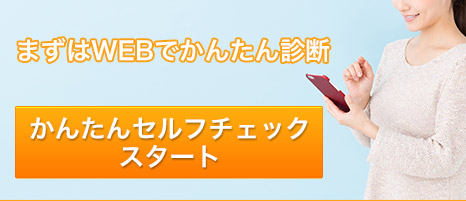息切れの原因・症状と鍼灸治療
息切れの原因

急な動作や激しい運動を行うと、どんな健康な人でも息切れが生じます。運動不足になると以前よりも早く息切れが生じるようになります。
このような息切れの場合は、明確な原因があるため、さほど問題ではありません。しかし、激しい運動をしているわけではなく、普通に生活している時に、突然息切れが起きる場合には、体に異常があると考えられます。
息切れは、心臓や肺、あるいは中枢神経や脳に異常を起こし、
体内の酸素が欠乏したときに生じます。
ここで息切れの主な原因をあげると、以下のようになります。
■呼吸器系の疾患
上気道、気管、気管支、肺などに生じる疾患。気管支炎、肺炎、
感染症(インフルエンザ)、肺癌、喉頭癌、喘息などが該当します。
■循環器系の疾患
血液やリンパを運び、体内を循環させる内臓器官に異常を伴う疾患。
高血圧、感染、心不全、狭心症、心筋梗塞、貧血、
不整脈、心筋症、心臓弁膜症が該当します。
■脳・神経の疾患
脳卒中や神経疾患を示します。パーキンソン病、脳腫瘍、脳梗塞、
くも膜下出血、脳内出血、更年期障害、自律神経失調症などが該当します。
上記のように、息切れには、重大な疾患が生じている場合があり、
注意が必要です。
息切れの症状

息切れの症状が出た場合に、医療機関が息切れの重症度を確認する方法として、「ヒュー・ジョーンズ分類」と呼ばれる確認法がよく用いられます。
ヒュー・ジョーンズ分類では、息切れの重症度を5段階に分けて分類します。
- 1 Ⅰ 同年齢の健康者と同様の労作ができ,歩行,階段昇降も健康者並みにできる。
- 2 Ⅱ 同年齢の健康者と同様に歩行できるが,坂道・階段は健康者並みにはできない。
- 3 Ⅲ 平地でも健康者並みに歩けないが,自分のペースなら1マイル(1.6km)以上歩ける。
- 4 Ⅳ 休み休みでなければ50m以上歩けない。
- 5 Ⅴ 会話・着替えにも息切れがする。息切れの為外出できない。
上記の分類は、数字が大きくなるほど症状が重くなります。
ヒュー・ジョーンズ分類は、息切れの度合いを確認する方法として
大変有効であり、多くの医療機関で用いられています。
西洋医学の治療

息切れの治療は、原因を特定することが極めて重要に
なります。
まず、呼吸器系か循環器系のどちらに異常があるかを特定し、どちらにも異常がなければ、脳・神経系統を検査することになります。
そこで検査をしても異常が見当たらず、息切れの原因が特定できない場合には、応急処置として以下の治療が行われます。
■酸素の注入
酸素の注入を行うことで、息切れの辛い症状を緩和させる方法。
簡易的な装置を自宅に設置する在宅酸素療法もあります。
■薬物の投与
薬を使って息切れの辛い症状を緩和させる方法。
代表的な薬として、モルヒネがあります。
呼吸器や循環器、もしくは脳系統に異常があった場合には、各専門医において
適切な治療を行うことになります。
近年増えているのが原因不明の息切れになります。
医療機関で精密検査を行ってもどの臓器にも異常がなく、息切れが起きる
患者さんが増えています。
原因不明の息切れの場合は、自律神経の異常が疑われるように
なります。
実は、自律神経失調症を患っている患者さんで
特に多い症状の一つに息切れがあります。
「じっとしているだけなのに、なぜか息苦しい」
「ちょっと動いただけで息切れをする」
という症状は自律神経失調症に見受けられる代表的な症状です。
ただ、自律神経失調症は、西洋医学では「腰痛」や「肩こり」
と同じような自覚症状として扱われています。
つまり、正式な病気として認められていないため、治療法が
確立されていないという現実があります。
鍼灸治療

息切れと自律神経は関係がないように思えますが、自律神経は人間の体の機能を正常にコントロールする重要な役割を果たしています。
自律神経が乱れると、体の機能が乱れ、体のどこで異常が起きてもけっしておかしくはないのです。息切れが慢性化している場合には、血流が悪化して体が常に緊張している状態でもあります。
鍼灸治療では、まず体の凝りを解消するツボに鍼を打ち、
体の凝りをほぐす治療を行います。
それと同時に、全身の状態を確認して、体のバランスが崩れている
部分に鍼を施し、全身のバランスを整える治療を行っていきます。
鍼を打つ場所は、人によって体の状態がまったく違うので、
患者さんにとって最適なツボに鍼を打ちます。
また、鍼灸には免疫力を高め、息切れの再発を防ぐ効果があります。
このように鍼灸は、血流の改善や筋緊張の緩和を実現し、交感神経と副交感神経の
二つの自律神経を整えることで、息切れの根本原因を取り除く治療を行います。
どの医療機関に行っても治らない息切れは、自律神経失調症の
疑いが強いです。長年、慢性的な息切れに悩まれている方は、一度、
鍼灸をお試しすることをお勧めします。